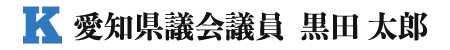令和7年総務企画委員会 本文 2025-07-02
【黒田太郎委員】
諮問第1号及び第2号、退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について伺う。
まず、審査請求人2人の主張と処分庁の主張における主な争点を詳しく伺う。
【人事課担当課長(総務・給与)】
審査請求人と処分庁双方の主な主張については、諮問第1号、諮問第2号ともに、本日配付している採決書案の概要の1ページ目の下段から2ページ目の上段にかけて記載している。
最初に、諮問第1号の概要資料、下段の当事者の主な主張の概要欄を見てもらいたい。
こちらについて、上司である職員の主張は主に三点ある。
一点目については、部下職員に対して行った指示、具体的に話すと、高齢男性を管轄区域外に移送し、そこで名前を名乗らず119番通報すること、また、救急隊には接触しないようにする旨の指示は、医療機関へつなごうと提案したものであり、保護責任の放棄をもくろんだものではないと主張している。次に、二点目、2ページ目であるが、高齢男性が地面に倒れた状態で放置されたことは事後に部下職員から聞かされたものであり、そのことも含め、隠ぺいとされたことは承服できないと主張している。三点目は、一定程度の退職手当の減額はやむを得ないが、賃金の後払い的要素まで剥奪され、全額不支給とされることは納得できないと主張している。
これに対し、処分庁の主張は、一点目については、上司の指示は生活保護法による保護の放棄を惹き起こさせるものであり、高齢男性への安全性を妨げるものであること。二点目については、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしたものであることから、ともに悪質性が高いと主張している。そして、三点目については、一部不支給の基準を定めた退職手当の条例運用通知の中で、職務に関連した非違行為や非違を隠ぺいする行動を取った場合には処分を重くすることが示されており、本件事案は一部不支給とする場合には該当せず、違法または不当な点はないと主張している。
次に、諮問第2号の概要資料、下段の当事者の主な主張の概要欄を見てもらいたい。
こちらは部下である職員の主張である。こちらについても主に三点ある。
一点目と二点目は、深夜、身元不明、高齢者、マニュアルもないという対応困難な状況下での置き去り行為や虚偽説明は上司の指示に従ったものであり、やむを得なかったと主張している。そして、三点目については、民間の裁判例では安易な全部不支給は許されておらず、著しく信義に反する行為があったか否かが審理されるべきであると主張している。
これに対し処分庁は、一点目については、重大かつ明白な瑕疵である上司の指示に従う義務はないこと、様々な方法を検討することなく、置き去りという方法を選択したことはあり得ない行為であると主張している。二点目については、虚偽説明は保護を放棄したことを隠す目的で行われたものであり、加えて、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしたものであることから、悪質性が高いと主張している。そして、三点目については、資料では最高裁判例を引用しているので、簡潔に言うと、公務に対する信頼への影響など、公務員固有の事情を重視することは否定されていないことが判例で示されているなど、公務員の退職手当における不支給の判断基準は民間と異なるものであると主張している。
【黒田太郎委員】
審査庁としては、これら審査請求人と処分庁双方の主張を踏まえて判断が行われたものと認識しているが、諮問第2号における部下職員の主張にもあるとおり、深夜、身元不明、高齢者という通常起こらない対応困難な状況下で、マニュアルもない中で発生した事案であることも事実である。こうした事実も含め、十分な審理、判断がなされたのか伺う。
【人事課担当課長(総務・給与)】
審査庁としては、先ほど黒田太郎委員から指摘のあった今回の事案が、深夜、身元不明、高齢者、マニュアルもないなど、対応困難な状況であったことは、双方の主張のほか、事案発生後における福祉局の検証結果などにより確認し、認めている。しかしながら、双方の主張を確認し、慎重に審理を進める中において、やはり対応困難な状況下であっても、職員2人は生活保護を担当する職員でありながら、様々な方法を検討せず、生活保護法による保護の放棄という少なくとも選択すべきではない対応を行ったものであり、また、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしており、悪質性が高いものであると考えている。加えて、それらが大きく報道され、公務に対する信頼への影響も見過ごすことはできない。よって、処分を軽減すべき事情は認められないと審査庁としては判断した。
【黒田太郎委員】
債券運用による含み損の問題を取り上げる。
これは新聞報道であるが、地方公共団体の基金において債券運用による含み損が出ているという報道があった。これは金利が上がってきていることで債券の価格が逆に下がってきている。つまり、過去に買った債券は、その価格を評価すると買ったときよりもマイナスになってきていると、このような状況だと思う。このために、県の基金の運用状況について確認したい。
まず一つ目、県の基金ではどのような資金運用を行っているのか。
【資金企画課長】
資金企画課では、満期一括償還分の減債基金以外の基金については一元的に運用しており、大口の定期預金により運用している。また、満期一括償還分の減債基金については、県債の満期一括償還に備えるため、総務省の定めたルールに基づいて積み立てた分について、地方債等の債券による長期運用を中心に運用している。
【黒田太郎委員】
今、基金の一元的な運用と答弁があったが、この基金の一元的な運用はどのように行っているか。
【資金企画課長】
基金の一元的な運用については、25の基金を大口の定期預金により運用している。運用期間は原則1年を上限としており、運用に当たっては一口を50億円として、定期預金先を複数の金融機関から引き合いにより預入利率を提示してもらい、高い利率を提示した金融機関を選定している。2024年度に預け入れた額については合計で2,700億円となっている。
【黒田太郎委員】
次であるが、満期一括償還分の減債基金、これは債券で運用しているとのことだが、この債券運用はどのように行っているのか。
【資金企画課長】
満期一括償還分の減債基金の債券運用については、債券を満期まで保有することで元本と運用益を確実に確保している。運用の具体的な手法としては、金利の変動リスクを平準化し、長期的に安定した運用益が確保できるようにするため、将来にわたって各年度に満期を迎える債券の残高が一定となるように投資するラダー型運用という手法により行っている。2024年度末の時点で運用している債券の残高は7,907億円となっている。
【黒田太郎委員】
ラダー型、少し難しいが、今の満期一括償還分の減債基金の債券運用で私が一番確認したいのは、要は減債基金なので、いつ幾らお金が必要だということが完全に計画を立てることができるので、それに合わせて債券を買って運用していく、そのような運用の仕方と理解してよいか。
【資金企画課長】
そのとおりである。
まず、債券運用における、いわゆる含み損とは、黒田太郎委員が示したとおり、債券の取得価格よりも売却価格のほうが低くなり、満期を迎える前に売却する場合は売却損が出る状態のことをいうと認識している。含み損がある債券についても、満期まで保有する場合は元本と利回りを確保することができ、損失は発生しない。
黒田太郎委員が冒頭で述べたように、含み損が問題となっている地方公共団体においては、財源が不足して基金を取り崩す必要がある場合にやむを得ず、満期を迎える前に債券を売却して含み損を確定した上で取崩しを行うことを検討する必要があるのではないかと認識している。一方、本県においては、満期一括償還分の減債基金において債券運用を行っている。この基金は、発行した県債の満期一括償還に備えるため、必要額を積み立てるものであり、債券運用可能な期間、債券運用可能な規模は明確である。また、県債の償還以外の目的で取り崩して活用することもない。したがって、全ての債券を満期まで保有する形で運用できることから、本県においては債券の含み損について想定する必要はなく、問題はないと考えている。
【黒田太郎委員】
減債基金を運用するために債券を保有し運用するわけであるから、それを今評価してほしいといって評価すると、もしかすると含み損があるのかもしれないが、愛知県のこの運用の仕方からすると、これはもう途中で売ることがない、満期まで持つ、つまり問題ないという理解でよいか。自分の言葉で言い直したが、確認したい。
【資金企画課長】
そのとおりであり、本県においては問題ないと認識している。
【黒田太郎委員】
金利が少しずつ上昇してきているので、それぞれの運用益、これはやはり増加してきていると思うが、これも確認したい。
【資金企画課長】
まず、基金の一元的な運用における大口定期預金による2024年度の運用益については約9億円と見込んでおり、2023年度の約3億円から6億円増加している。
また、満期一括償還分の減債基金の債券運用による2024年度の運用益については約38億円と見込んでおり、2023年度の約26億円から12億円増加している。
今後も引き続き安全な資金運用を第一としながら、確実な運用益を確保できるよう基金の効果的な運用に取り組んでいく。
【黒田太郎委員】
要望する。金利が上昇する中で堅実な運用方法で着実に運用益を上げており、このことは大変すばらしいことだと思う。ただ一方で、金利が上がっていくと県債の利払い、これも増えていくことになる。引き続き、この資金の運用と調達の両面で効果的な取組を着実に進めてもらいたい。運用益を上げようと思うとどうしても堅実さが損なわれてしまう。堅実さにこだわっていこうと思うと逆に運用益は上がらなくなる。ここの部分を上手に県としてぎりぎりの線を追求して運用してもらえればと思う。
諮問第1号及び第2号、退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問について伺う。
まず、審査請求人2人の主張と処分庁の主張における主な争点を詳しく伺う。
【人事課担当課長(総務・給与)】
審査請求人と処分庁双方の主な主張については、諮問第1号、諮問第2号ともに、本日配付している採決書案の概要の1ページ目の下段から2ページ目の上段にかけて記載している。
最初に、諮問第1号の概要資料、下段の当事者の主な主張の概要欄を見てもらいたい。
こちらについて、上司である職員の主張は主に三点ある。
一点目については、部下職員に対して行った指示、具体的に話すと、高齢男性を管轄区域外に移送し、そこで名前を名乗らず119番通報すること、また、救急隊には接触しないようにする旨の指示は、医療機関へつなごうと提案したものであり、保護責任の放棄をもくろんだものではないと主張している。次に、二点目、2ページ目であるが、高齢男性が地面に倒れた状態で放置されたことは事後に部下職員から聞かされたものであり、そのことも含め、隠ぺいとされたことは承服できないと主張している。三点目は、一定程度の退職手当の減額はやむを得ないが、賃金の後払い的要素まで剥奪され、全額不支給とされることは納得できないと主張している。
これに対し、処分庁の主張は、一点目については、上司の指示は生活保護法による保護の放棄を惹き起こさせるものであり、高齢男性への安全性を妨げるものであること。二点目については、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしたものであることから、ともに悪質性が高いと主張している。そして、三点目については、一部不支給の基準を定めた退職手当の条例運用通知の中で、職務に関連した非違行為や非違を隠ぺいする行動を取った場合には処分を重くすることが示されており、本件事案は一部不支給とする場合には該当せず、違法または不当な点はないと主張している。
次に、諮問第2号の概要資料、下段の当事者の主な主張の概要欄を見てもらいたい。
こちらは部下である職員の主張である。こちらについても主に三点ある。
一点目と二点目は、深夜、身元不明、高齢者、マニュアルもないという対応困難な状況下での置き去り行為や虚偽説明は上司の指示に従ったものであり、やむを得なかったと主張している。そして、三点目については、民間の裁判例では安易な全部不支給は許されておらず、著しく信義に反する行為があったか否かが審理されるべきであると主張している。
これに対し処分庁は、一点目については、重大かつ明白な瑕疵である上司の指示に従う義務はないこと、様々な方法を検討することなく、置き去りという方法を選択したことはあり得ない行為であると主張している。二点目については、虚偽説明は保護を放棄したことを隠す目的で行われたものであり、加えて、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしたものであることから、悪質性が高いと主張している。そして、三点目については、資料では最高裁判例を引用しているので、簡潔に言うと、公務に対する信頼への影響など、公務員固有の事情を重視することは否定されていないことが判例で示されているなど、公務員の退職手当における不支給の判断基準は民間と異なるものであると主張している。
【黒田太郎委員】
審査庁としては、これら審査請求人と処分庁双方の主張を踏まえて判断が行われたものと認識しているが、諮問第2号における部下職員の主張にもあるとおり、深夜、身元不明、高齢者という通常起こらない対応困難な状況下で、マニュアルもない中で発生した事案であることも事実である。こうした事実も含め、十分な審理、判断がなされたのか伺う。
【人事課担当課長(総務・給与)】
審査庁としては、先ほど黒田太郎委員から指摘のあった今回の事案が、深夜、身元不明、高齢者、マニュアルもないなど、対応困難な状況であったことは、双方の主張のほか、事案発生後における福祉局の検証結果などにより確認し、認めている。しかしながら、双方の主張を確認し、慎重に審理を進める中において、やはり対応困難な状況下であっても、職員2人は生活保護を担当する職員でありながら、様々な方法を検討せず、生活保護法による保護の放棄という少なくとも選択すべきではない対応を行ったものであり、また、10日間にわたり虚偽説明を重ね、事実を隠ぺいしており、悪質性が高いものであると考えている。加えて、それらが大きく報道され、公務に対する信頼への影響も見過ごすことはできない。よって、処分を軽減すべき事情は認められないと審査庁としては判断した。
【黒田太郎委員】
債券運用による含み損の問題を取り上げる。
これは新聞報道であるが、地方公共団体の基金において債券運用による含み損が出ているという報道があった。これは金利が上がってきていることで債券の価格が逆に下がってきている。つまり、過去に買った債券は、その価格を評価すると買ったときよりもマイナスになってきていると、このような状況だと思う。このために、県の基金の運用状況について確認したい。
まず一つ目、県の基金ではどのような資金運用を行っているのか。
【資金企画課長】
資金企画課では、満期一括償還分の減債基金以外の基金については一元的に運用しており、大口の定期預金により運用している。また、満期一括償還分の減債基金については、県債の満期一括償還に備えるため、総務省の定めたルールに基づいて積み立てた分について、地方債等の債券による長期運用を中心に運用している。
【黒田太郎委員】
今、基金の一元的な運用と答弁があったが、この基金の一元的な運用はどのように行っているか。
【資金企画課長】
基金の一元的な運用については、25の基金を大口の定期預金により運用している。運用期間は原則1年を上限としており、運用に当たっては一口を50億円として、定期預金先を複数の金融機関から引き合いにより預入利率を提示してもらい、高い利率を提示した金融機関を選定している。2024年度に預け入れた額については合計で2,700億円となっている。
【黒田太郎委員】
次であるが、満期一括償還分の減債基金、これは債券で運用しているとのことだが、この債券運用はどのように行っているのか。
【資金企画課長】
満期一括償還分の減債基金の債券運用については、債券を満期まで保有することで元本と運用益を確実に確保している。運用の具体的な手法としては、金利の変動リスクを平準化し、長期的に安定した運用益が確保できるようにするため、将来にわたって各年度に満期を迎える債券の残高が一定となるように投資するラダー型運用という手法により行っている。2024年度末の時点で運用している債券の残高は7,907億円となっている。
【黒田太郎委員】
ラダー型、少し難しいが、今の満期一括償還分の減債基金の債券運用で私が一番確認したいのは、要は減債基金なので、いつ幾らお金が必要だということが完全に計画を立てることができるので、それに合わせて債券を買って運用していく、そのような運用の仕方と理解してよいか。
【資金企画課長】
そのとおりである。
まず、債券運用における、いわゆる含み損とは、黒田太郎委員が示したとおり、債券の取得価格よりも売却価格のほうが低くなり、満期を迎える前に売却する場合は売却損が出る状態のことをいうと認識している。含み損がある債券についても、満期まで保有する場合は元本と利回りを確保することができ、損失は発生しない。
黒田太郎委員が冒頭で述べたように、含み損が問題となっている地方公共団体においては、財源が不足して基金を取り崩す必要がある場合にやむを得ず、満期を迎える前に債券を売却して含み損を確定した上で取崩しを行うことを検討する必要があるのではないかと認識している。一方、本県においては、満期一括償還分の減債基金において債券運用を行っている。この基金は、発行した県債の満期一括償還に備えるため、必要額を積み立てるものであり、債券運用可能な期間、債券運用可能な規模は明確である。また、県債の償還以外の目的で取り崩して活用することもない。したがって、全ての債券を満期まで保有する形で運用できることから、本県においては債券の含み損について想定する必要はなく、問題はないと考えている。
【黒田太郎委員】
減債基金を運用するために債券を保有し運用するわけであるから、それを今評価してほしいといって評価すると、もしかすると含み損があるのかもしれないが、愛知県のこの運用の仕方からすると、これはもう途中で売ることがない、満期まで持つ、つまり問題ないという理解でよいか。自分の言葉で言い直したが、確認したい。
【資金企画課長】
そのとおりであり、本県においては問題ないと認識している。
【黒田太郎委員】
金利が少しずつ上昇してきているので、それぞれの運用益、これはやはり増加してきていると思うが、これも確認したい。
【資金企画課長】
まず、基金の一元的な運用における大口定期預金による2024年度の運用益については約9億円と見込んでおり、2023年度の約3億円から6億円増加している。
また、満期一括償還分の減債基金の債券運用による2024年度の運用益については約38億円と見込んでおり、2023年度の約26億円から12億円増加している。
今後も引き続き安全な資金運用を第一としながら、確実な運用益を確保できるよう基金の効果的な運用に取り組んでいく。
【黒田太郎委員】
要望する。金利が上昇する中で堅実な運用方法で着実に運用益を上げており、このことは大変すばらしいことだと思う。ただ一方で、金利が上がっていくと県債の利払い、これも増えていくことになる。引き続き、この資金の運用と調達の両面で効果的な取組を着実に進めてもらいたい。運用益を上げようと思うとどうしても堅実さが損なわれてしまう。堅実さにこだわっていこうと思うと逆に運用益は上がらなくなる。ここの部分を上手に県としてぎりぎりの線を追求して運用してもらえればと思う。