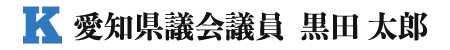令和7年6月定例会(第3号) 本文 2025-06-24
◯三十七番(黒田太郎君)
あいち民主の黒田太郎です。
私からは大きく四つの質問をさせていただきます。
まず初めに、不耕起V溝直播栽培による米作りについてです。
私たちが今、生活する上で直面している課題の一つに、物価高があります。この課題に対して、国も自治体も様々な対策を講じているわけですが、物価高の生活への影響を緩和するには、一、収入を増やすこと、そして、二、物価を下げることのいずれかないしは両方を行う必要があるわけですが、私は今回の質問の中で、後者の物価を下げることについて考えてみたいと思っています。
では、物価を下げるにはどうすればいいのでしょうか。これも単純に考えると二つの手段があり、一、供給量を増やすか、二、生産コストを下げるか、いずれかないし両方を行うと、物価は下がることになります。
そして、今、物価高で私たちの生活を圧迫しているその象徴的な品といえば、それは米ではないでしょうか。
そこで、私は、米の値段を下げるため、米の生産コストを下げることができないかを考えてみました。
このことを考える際に、大変印象的な記事がありましたので、御紹介させていただきます。
週刊ダイヤモンドの二〇二四年五月十一日号には、埼玉県にある農業法人のヤマザキライスでは、玄米一キロを生産するのにかかる費用が七十五円、全国平均の費用は二百四十六円と書かれていました。そして、この経費節減を実現した栽培方法が乾田直播であるとのことです。
この乾田直播については、週刊ダイヤモンドの二〇二五年四月五日号にも取り上げられており、そこには植物活性剤などを併用して乾田直播栽培を行うと、稲作には不向きとされていた北海道の畑作地帯でも米作りが可能になると書かれており、米耕作地拡大、つまり生産量増加の可能性についても触れられていました。
では、乾田直播による米作りとはどういうものか確認してみます。漢字がまさに乾いた田んぼに直接まくということからも分かるとおり、畑状態の田に種子をまき、苗が立ってきたところで水を入れるという稲の栽培方法です。
一般的な水稲栽培では、まず、苗代で苗を作り、田では固まった土を掘り起こして空気に触れさせる田起こしを行った上で、もう一度さらに細かく砕き、田に水を張り、土とかき混ぜ、土の表面を平らにする代かきを行います。
この比較からも分かるとおり、乾田直播では苗を作る必要がなく、代かきも不要であるため、作業の省力化やコスト削減が期待できることになります。
ここで改めて乾田直播の長所を整理してみます。
まずは省力化です。
苗を育てる育苗、代かき、育った苗を田に植える移植が不要となるため、農家は他の作物の栽培や経営活動に時間を割けるようになります。
次に、コスト削減です。
育苗にかかるコストがなくなるほか、初期段階で田に水を張らないため、水管理のコストや水資源使用のコストが抑えられます。また、水使用量の削減により環境負荷が軽減されると考えられるほか、水を張っていない状態ではメタンガスの発生が少ないと言われており、これらの点で環境に優しいと考えられます。
もちろん、どんな物事も長所だけというわけにはいかず、短所もあります。乾田直播の短所を整理してみます。
まず、収穫量の年次変動が大きいと言われています。
また、田に水を張らない期間が長い分、雑草が育ちやすく、雑草管理が難しいと言われています。
さらに、新たな機械設備が必要なため、初期投資が大きいとも言われています。
加えて、乾田直播に適した品種が限られているとも言われています。
全体として、これまでの水田稲作とは異なる稲作であるため、技術の習得に難しさがあると言われています。
こうした短所があったとしても、長所が大きいなら、短所を克服して長所を伸ばしていく政策を実施すべきであると私は考えます。
そして、愛知県農業総合試験場では、乾田直播栽培の一種である不耕起V溝直播栽培を開発し、普及を図っているとのことです。
そこでお伺いします。
一、不耕起V溝直播栽培とはどのような栽培技術で、一般的な移植栽培の米作りに比べ、どの程度の省力化、低コスト化につながるのかお聞かせください。
二、不耕起V溝直播栽培による米作りについて、愛知県の普及状況、課題及び今後の取組方針についてお聞かせください。
次に、第二十回アジア競技大会における総合格闘技について伺います。
総合格闘技が来年のアジア競技大会の競技種目に追加されたと発表されました。この質問では、アジア・アジアパラ競技大会がより充実したものとなり、県民の皆様の税金を使って開催してよかったと思っていただける大会となることを願い、幾つかの問題点を指摘させていただきます。
まず、世界的に総合格闘技の団体は幾つかあるわけですが、来年のアジア競技大会の競技種目に追加された総合格闘技の団体は、アジア総合格闘技協会、アジアン・ミクスド・マーシャル・アーツ・アソシエーション──以下AMMA──であり、競技はAMMAが実施する形式で行われるとのことです。
しかし、このAMMAは総合格闘技の世界では本流ではありません。本流はあくまでも世界百二十か国以上が加盟する国際総合格闘技連盟、インターナショナル・ミクスド・マーシャル・アーツ・フェデレーション──以下IMMAF──であり、そのアジア支部がAMMAFとなりますので、このAMMAFが実施する形式で行われるのであれば、アジア競技大会の盛り上がりも期待ができます。
なぜならば、IMMAF形式で行われる総合格闘技は、二〇三二年のオリンピック種目になる可能性があり、その傘下であるAMMAFの形式で競技が行われれば、観客動員もかなりの数が期待できるからです。
また、団体としての歴史にも大きな差があり、AMMAは二〇二二年に設立されたのに対し、IMMAFは二〇一二年の設立と、十年の差があります。そうだとすると、国際的な大会を運営する上で、知識や技術、コツなどの蓄積に大きな差があると推察されます。
さらに、実は、愛知・名古屋は、IMMAF系列のアマチュア総合格闘技において非常に重要な地域なのです。なぜならば、IMMAFが毎年行う世界選手権において、その日本代表監督を務めるのは、名古屋市出身で名古屋にて道場を運営する方であり、その道場には、世界選手権にて銀メダルを獲得した山口怜臣選手が所属しているのです。
愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会にて、こうした実力ある、しかも名古屋にゆかりのある監督や選手が関与、参加できれば、大会の盛り上がりに大きく寄与するのではないでしょうか。
この点、AMMAの傘下に一般社団法人ジャパンAMMA協会が設立され、本年六月十四日の報道用資料には、今後は、アジア競技大会でのメダル獲得に向け、総合格闘技を愛する国内選手に広く呼びかけ、最強の代表選手を選考できますよう準備を進めてまいりますとありましたので、個人的には一筋の光を見た気持ちになりました。
そこでお伺いします。
アジア競技大会における総合格闘技は、申し上げましたような課題を抱えていることから、県としてよりよい競技とすべく、何らかの対応をすべきと思いますが、県のお考えをお聞かせください。
次に、創業者を孤立させない取組について伺います。
昨年十月末にSTATION Aiが始動し、約八か月となります。この質問では、県民の皆様からお預かりした税金で造ったこの施設を日本一、世界一の施設にして、県民の皆様に恩返しをするために、大切であると思われる視点を提供させていただきます。
まず、プレ・ステーションAiも含め、これまでのSTATION Aiプロジェクトでの支援を通じ、どのような成果が生まれているかお伺いします。
そして、仮にプレ・ステーションAiの時代を通じて、数字の上では順調にスタートアップ支援が行われているように見えたとしても、この数字からは分からない問題が潜んでいます。それが創業者の燃え尽き症候群と言われる問題であり、私がこの質問で訴えたいことなのです。
それでは、まず具体例として、私の知人の状況を、知人了承の下、以下に整理してみます。
知人は新卒で製薬企業に入社。その後、留学を決意し、一年半で退職。英国で大学院修了後、外資系製薬企業の研究開発職に就き、帰国。その後、こうした経験を生かして起業することを決意。約一年半の準備期間を経て、主に承認後の薬の評価やエビデンス創出に焦点を当てた臨床研究支援の会社を起業した。
当然のことながら、起業には苦労があり、知人を含めた三人で事業を開始。資金節約のため、民家を借り、オフィス兼住居にした。起業当時、知人の業務内容は欧米では珍しくなかったが、日本ではほとんど知られておらず、会社規模も小さく実績もなかったため、理念や狙いは理解されても、業務依頼にはつながらない日々が続いた。
しかし、知人は努力を重ね、二十一年の間に、製薬企業に加え、大学や研究機関、行政機関から数多くの依頼を受け、国内外で実績を構築した。
また、働きながら国内外の大学院にて博士号や修士号を取得するメンバーを輩出し、国際的な人材の採用や海外企業との業務提携も実現した。大学との共同研究講座にも参画し、個人的にも、大学の兼任講師として研究や教育活動にも従事した。年商十億円の目標を除けば、それ以外は起業時の目標をほぼ達成した。 こうして見ると、この起業は、世間一般的に見れば成功したと言えよう。
しかしながら、身体に変調を来した。仕事をしながら息絶えてもよいという精神状態で、睡眠時間は一日平均三時間、会社で寝泊まりするということもしばしばといった働き方を続けたところ、原因不明の発熱に悩まされたほか、アトピー性皮膚炎の症状が全身に広がり、仕事が手につかない状態になった。精神的にも不安定となり、大口の出資者から社長を譲れという宣告があったことで、断腸の思いで社長を交代することになった。
自分の異変に気づいていたにもかかわらず、アクセル全開のまま立ち止まらずに放置し、結局は心身がむしばまれ、燃え尽きてしまった。このような自身の経験を生かし、現在ではスタートアップやベンチャーの創業者向けにカウンセリングやコーチングプログラムを開発し、提供したいと考えている。
以上が知人の具体例ですが、これが知人に限った話ではなく、スタートアップの世界においてよく見られる問題であることが最近分かってきたようです。
二〇二三年三月、イスラエルのコンサルティング企業、Y・ベンジャミン・ストラテジック・マーケティング社は、創業者が抱えるストレスとその影響についてまとめた報告書、スタートアップ・スナップショット第七版を発表しました。
この報告書の骨子は以下のとおりです。
四四%の創業者が強いストレスを感じ、三六%が燃え尽きの状態にある。
五四%の創業者が自社の未来に強い不安を感じている。
八一%の創業者が自身のストレスや不安についてあまり周囲に打ち明けられていない。
投資家に自分が抱えているストレスについて話すと回答した創業者は僅か一〇%。
カウンセリングやコーチングを受けている創業者は二割にすぎない。
そして、報告書のサマリーには、イノベーションの精神を持つ創業者たちだが、ストレスケアという点においては過去にとらわれていると書かれているとのことです。
米国では、スタートアップ企業の創業者のストレス対策を講じる動きが生まれているようです。例えば、投資家とスタートアップ創業者たちがメンタルヘルスケアの推進を宣誓するウェブページ、ファウンダー・メンタルヘルス・プリッジを公開したとのこと。このページには既に六百五十三名もの投資家や創業者が署名し、メンタルヘルスをビジネスの優先事項として取り組むことを表明しているようです。これは二〇二三年十一月現在です。
このように、華やかに見えるスタートアップの世界ですが、創業者の精神状況、特に燃え尽き症候群といった問題が着目され始めています。そして、燃え尽き症候群は創業者の抱える孤立感が大きな要因の一つと考えられます。
STATION Aiもこうした問題について配慮がなされれば、まさに日本一、世界一のスタートアップ支援拠点に進化していくのではないでしょうか。
そこでお伺いします。
創業者を孤立させないような取組として、STATION Aiではどのような支援を行い、成長支援につなげているのかお伺いします。
結びの質問は、死因究明拠点整備モデル事業についてです。
我が国は多死社会へ急速に移行しており、それは愛知県でも同じことです。
人口動態統計によりますと、愛知県内の二〇一四年の死亡者数は六万二千四百二十六人であり、これが二〇二四年の概算では八万二千六百九人と、この十年で二万人以上の増加があり、率にすると三二・三%も増えています。これが二〇四〇年には九万人を超えるとの予測もあるようです。
では、死亡者数が増えると、我々の社会にどのような影響が出てくるのでしょうか。これについては幾つもの影響がある中で、この質問では死因究明体制が追いついていかないのではないかという点に絞って考察してまいります。
それでは、死因を不明なままにしておくと、どのような問題が生じるのか、具体例を挙げて考えてみます。
例えば、独り暮らしの高齢者が自宅で死亡する、いわゆる孤独死の場合、遺体が数日後に発見されることがあり、その場合は検死──これは警察による検視と医師による死体検案の双方を含む──が困難で、死因が不詳とされたり、心不全などの曖昧な死因で済まされてしまうことがあります。
しかし、死因が熱中症と確定できれば、エアコン設置支援という政策につながり、栄養失調と確定できれば、見守り訪問強化という政策につながり、服薬中断と確定できれば、配食・服薬支援の導入といった政策につながるといったように、具体的な政策につながるはずなのです。
また、例えば、糖尿病による死亡に地域差があることが正確に把握できていれば、地域別にきめの細かい生活習慣の改善指導を行うことができ、どの地域にも同じ指導を行ったときと比べて、指導の効果がより高まると推測されます。
このようにして考えると、死因の見える化は政策の羅針盤であると言えるのではないでしょうか。死因が不明なまま遺体を火葬することは、地域の健康課題を知るためのデータが焼失することを意味します。
こうした意味で、死因究明体制の整備は、医療、福祉、公衆衛生の方向性を示す羅針盤を県政に設置するための投資であり、多死社会に対応するための基幹インフラ整備であると言えるのではないでしょうか。
では、死因は現状、どの程度正確に把握できているのでしょうか。
警察庁の死体取扱状況によれば、二〇二四年に愛知県警が取り扱った死体数は九千三百十九体、このうち解剖された数は四百五十四体、解剖率は四・九%と、全国平均九・八%に比べて低くなっています。
しかし、解剖以外にも遺体をCTでスキャンする死後CTという検証方法があり、これは約三千体行われています。この死後CTは死因究明における重要な情報源として活用されており、一定程度、死因の絞り込みや判定の精度向上に貢献していると考えられます。したがって、解剖と死後CTを加えた三千五百体は、かなり詳細な死因が把握できていることになります。
しかし、残りの約六千体の死体については、臨床医による検案などを基に死因が判断されており、これらが公衆衛生や予防医学の観点から十分な精度を持って死因特定がなされているとは限らないという課題も指摘されています。 また、昨年の死者数が八万二千六百九であり、そのうち、警察が取り扱った死体数が九千三百十九であるため、その差の約七万三千体については、事件性がなく、病院などで亡くなられたことによるものですが、臨床現場では医師の経験と判断に基づいた診断が行われており、制度としての検証体制が十分に整っているとは言い難く、老衰や心不全などの包括的な診断名で処理される例も少なくありません。その結果、公衆衛生上の課題や地域の疾病実態が統計上で捉えにくくなるという問題が指摘されています。
このように、警察が取り扱う遺体も、それ以外の遺体も、医療、福祉、公衆衛生の観点からの死因究明が十分にはなされていないという点については、愛知県に限った問題ではありません。
こうした実態を受けて、厚生労働省では、死因究明等の実施に係る体制の充実強化は喫緊の課題と認識し、死因究明等推進計画を二〇二一年六月一日に閣議決定、二〇二二年度から死因究明拠点整備モデル事業を実施しています。
この事業には、一、検案・解剖拠点モデル事業と、二、薬毒物検査拠点モデル事業の二つが含まれていますが、本質問では前述の流れを受けて、一について取り扱わせていただきます。
そして、検案・解剖拠点モデル事業とは、この募集要項の取組の具体イメージのところに、都道府県警察、法医学教室、地元医師会等の地域における死因究明に取り組む関係者と連携・協力の上、都道府県知事部局等に死因究明拠点を設置するとあります。
愛知県として、ぜひともこのモデル事業に手を挙げていただきたいというのが、私がこの質問において強く訴えたいことなのです。
死因の見える化は政策の羅針盤、死因究明体制の整備は多死社会に対応するための基幹インフラ構築と申しましたが、もう少し具体的に、県がこのモデル事業を進め、死因究明体制を整備したときの利点、欠点を整理してみます。
まず、利点です。
一、御遺族の心理的、法的負担が軽減されます。
死因が不明なままでは、なぜ亡くなったのかという最も根源的な疑問が残り、遺族にとっては深い心理的負担となります。また、相続や保険等の法的手続にも支障を来すことがあります。
二、社会的リスクの見逃しが軽減されます。
例えば、独り暮らしの高齢者の死亡原因が不詳とされれば、本当は熱中症や栄養失調、服薬中断などがあったとしても見逃されます。すると、県としてどこに何をどれだけ支援すべきかが分からず、見守り支援や配食サービスといった施策が的外れになり、結果として税金の浪費にもつながります。
三、地域課題、環境リスクへの対応を早めます。
ある地域で特定の病気による死亡が増えていたとしても、死因が不明なままではその傾向に気づくことができません。仮に環境汚染や新たな感染症が背景にあった場合でも、早期対策が打てず、後手対応になってしまうおそれがあります。
四、医療の質を向上させます。
医療機関での急死や手術中の死亡においても、解剖による検証がなければ、医療の質向上や医療事故の防止に資する情報還元がなされません。
五、虐待、ネグレクトの兆候見逃しを防ぎます。
家庭内での死亡や介護中の急変の中には、一見、自然死に見えても、実は虐待やネグレクトが隠れていることもあります。適切な死因究明が行われなければ、こうした見えにくい人権侵害が放置されてしまう危険があります。
六、警察の負担が軽減されます。
検査施設において、遺体搬送、検案及び遺体の引渡し等を集約して行うことで、現状、警察官が行っている搬送等の業務が不要となります。
七、災害時などの遺体渋滞が緩和されます。
遺体渋滞とは、大規模災害時に多数の死者が短期間に発生することで、遺体の収容、搬送、検視・検案、安置、引渡しに至る一連のプロセスが円滑に進まず、深刻な滞留状態が生じることを指し、昨年元日に発災した能登半島地震をはじめ、大規模災害時に発生する深刻な問題です。
では、県にとっての欠点は何でしょうか。それは、財政支出を伴うということかと思います。
しかし、県民の皆様からお預かりする税金を何に使うか考えるとき、単に支出を支出とだけ片道で捉えるのではなく、その支出によって県民の皆様にどのような便益がもたらされるのかを考えるべきで、そうした観点で見れば、上記七つの利点は財政支出に十分資する利点と言えるのではないでしょうか。
そこでお伺いします。
愛知県として、死因究明拠点整備モデル事業にどのように対応していくお考えか、お聞かせください。
以上で、私の壇上からの質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◯農業水産局長(松井直樹君)
不耕起V溝直播栽培についてのお尋ねのうち、初めに、不耕起V溝直播栽培がどのような栽培技術で、どの程度の省力化、低コスト化につながるのかについてお答えします。
不耕起V溝直播栽培は、米作りの省力化と経費の削減を目指して、県農業総合試験場が一九九四年に開発しました。現在、全国二十三の道府県で導入されている栽培技術となっております。
この技術の特徴は、春先に乾いた田を耕さず、専用の機械でV字型の溝を切り、その溝に種もみと肥料を同時に直接まくところにあります。また、種もみが成長し、田に水を入れた後は収穫まで水を抜かずに栽培することから、水管理の省力化と夏の高温対策に効果があります。
このように、不耕起V溝直播栽培は、一般的な米作りに比べ、育苗や田植の作業が不要となり、水管理の手間も省けることなどから、労働時間が約三割削減できます。また、育苗資材が不要となることなどから経費が約一割削減でき、省力化と低コスト化を兼ね備えております。
次に、不耕起V溝直播栽培について、愛知県内の普及状況、課題、今後の取組方針についてお答えします。
不耕起V溝直播栽培は、省力化や低コスト化、さらには栽培時期の分散などのメリットがあることから、大規模な経営体を中心に、二〇二四年は県内の作付面積の約一五%に当たる約三千八百ヘクタールで取り組まれております。
不耕起V溝直播栽培を実施する上での課題としましては、専用の機械導入のために初期投資が必要であることや、春先に田に水を張らない期間が長く、雑草が生えやすいといったことがあります。
こうしたことから、機械導入に際して国や県の補助事業により支援するとともに、現在、農業総合試験場と民間企業が協力して開発を進めている雑草対策技術の早期実用化を図るなど、農業者が取り組みやすい環境を整え、米作りの省力化、低コスト化につながる不耕起V溝直播栽培の導入拡大を今後とも推進してまいります。
◯アジア・アジアパラ競技大会推進局長(舛田崇君)
第二十回アジア競技大会における総合格闘技についてお答えいたします。
総合格闘技につきましては、昨年九月に開催されたアジア・オリンピック評議会(OCA)と組織委員会が準備の進捗状況等について協議、調整を行う調整委員会の第二回会議において、OCAから実施協議に追加するよう要請がありました。
これを受け、組織委員会理事会での報告を経て、本年五月開催の第三回OCA調整委員会において、コンバットスポーツの一種別として追加することが決定されたところでございます。
一方、総合格闘技には複数の競技団体があり、それぞれの団体が大会を主催し、競技運営等を行っています。
アジア競技大会においては、OCA憲章により、OCAが承認した機関が技術面の運営の責任を負うと規定されていることから、愛知・名古屋二〇二六大会では、OCAに承認されたアジア総合格闘技協会と組織委員会が責任を持って競技を実施するものと認識しております。
また、日本選手団の派遣につきましては、本年五月に設立された一般社団法人ジャパンAMMA協会により、選手の選考を行うことが公表されております。 総合格闘技がアジア競技大会の正式競技として実施されるのは、愛知・名古屋二〇二六大会が初めてとなります。
県といたしましても、日本代表選手が活躍し、競技が大いに盛り上がるよう、選手の派遣を行う日本オリンピック委員会に対し、選手強化やトップクラスの選手派遣について要請を行ってまいります。
さらに、この初開催の競技をより多くの方に会場で御覧いただけるよう、地域のイベントなどを通じて、県民の皆様への周知も図ってまいります。
大会の開催に向け、組織委員会や競技団体など関係者一体となり、総合格闘技のみならず、全ての競技がベストな状態で行われるよう、準備を進めてまいります。
◯経済産業局長(犬塚晴久君)
STATION Aiプロジェクトにおける成果についてお答えいたします。
県では、二〇一八年十月に策定したAichi─Startup戦略に沿って、ハード・ソフト両面で起業家の裾野の拡大から創業、その後の事業展開に至るそれぞれのステージにおける支援や、地域全体のスタートアップ・エコシステムの醸成に努めてまいりました。
二〇二〇年一月に開設したプレ・ステーションAiでは、創業期、事業化初期を中心とした支援を実施し、昨年十月にオープンしたSTATION Aiでは、海外展開や事業会社とのオープンイノベーションを含む事業拡大も含めたオールステージに支援対象を拡充し、引き続き、切れ目ない支援に取り組んでおります。 これまでのSTATION Aiプロジェクトにおける支援を通じて、百五十七件の起業、百四十五件の資金調達、五十六件の人材採用、七十三件の事業会社との事業連携に加え、スタートアップの出口戦略、いわゆるエグジットとして、二件のM&A、一件の株式公開といった事例も出てきております。
具体的には、AIを活用した越境ECプラットフォームを展開する株式会社サゾが今年五月に七億一千万円を資金調達し、現在、STATION Aiに本社を構え、事業展開を進めております。
また、eスポーツ大会支援ツールの開発・運営事業を手がけていた株式会社パピヨンが上場企業へ事業売却、いわゆるM&Aを実現したほか、小型ドローンの開発、画像データの解析サービスを展開する株式会社リバラウェアが東証グロース市場へ上場、株式公開いたしました。
今後とも、こうした取組を一層強化し、スタートアップの創出、育成、事業拡大をしっかりと支援してまいります。
次に、STATION Aiにおける創業者を孤立させない取組についてお答えいたします。
創業者が事業を立ち上げ、成長させていく過程では、資金調達、人材確保、知的財産保護、社内ガバナンスの確立といった様々な課題を乗り越えていく必要があり、そのためには創業者の孤立を防ぎ、精神的なフォローや仲間づくりを支援していくことが大変重要と認識しております。
このため、STATION Aiでは、コミュニティマネージャーを配置し、日常の相談対応のほか、毎月、創業者にマンツーマンで事業の進捗状況を聞き取るマンスリーアップデートの機会を捉え、ビジネス面の相談に加え、心身面の状態把握やフォローを行っております。
また、会員専用のコミュニティツールを活用し、会員同士の対話や交流イベントへの参加、個別相談への活用を促すなど、お互いの知識、経験を共有し、解決につなげていく環境づくりに努めております。
さらに、テーマを定めて十五人から二十人程度のより小規模で密に交流できるコミュニティーとして、ギルドと呼ぶ制度を運営しております。このギルドの中からは、自らの悩み、課題を創業者同士で共有し、先輩起業家の経験やアドバイスも聞きながら、課題を克服し、成長していくことを目指す活動も出てきております。
今後とも、創業者が創業者同士、専門家、先輩起業家と情報共有し、相談しやすい環境づくりに努め、より多くのスタートアップの成長支援に取り組んでまいります。
一点、訂正させていただきます。
先ほど、小型ドローンの開発、画像データの解析サービスを展開する株式会社の名前につきまして、私、リベラウェアと申し上げましたが、リバラウェアの間違いでございました。訂正させていただきます。失礼いたしました。
◯保健医療局長(長谷川勢子君)
死因究明拠点整備モデル事業への本県の対応についてお答えします。
死因究明は、災害、事故、犯罪等における被害の拡大や再発防止に寄与するとともに、疾病予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上に資する情報として活用されるなど、公益性の高い取組であると認識しております。
国が実施する死因究明拠点整備モデル事業は、公衆衛生の観点から解剖や検査等が適切に実施される体制の構築を目指す取組で、二〇二二年度の事業開始から毎年度、二、三か所の自治体、大学で、検案及び解剖のモデル事業が実施されております。
しかしながら、モデル事業の実施結果を見ますと、解剖や検査の件数は年間で数件程度にとどまっており、その要因として、画像診断医や解剖医の不足、協力検案医の確保、警察との連携等挙げられております。
さらに、こうした要因以外にも、遺体の搬送体制の整備や、遺族の理解と同意など、整理すべき課題は少なくありません。
このように、モデル事業の実施については、県警察、大学の法医学教室、県医師会などとの連携、協力が不可欠となりますので、関係機関の意見を伺いながら、しっかり研究してまいりたいと考えております。
◯経済産業局長(犬塚晴久君)
失礼いたしました。先ほど企業名の訂正をさせていただきましたけれども、正しくは小型ドローンの開発、画像データの解析サービスを展開する株式会社リベラウェア、リベラウェアが正しい名前でございました。失礼いたしました。
◯三十七番(黒田太郎君)
それぞれに御答弁ありがとうございました。
それでは、一点、要望させていただきます。
死因究明拠点整備モデル事業についてでございます。
答弁を聞き、残念な気持ちになりました。死因という今後の政策立案にとって極めて重要な情報が十分に把握されていないにもかかわらず、この状況を積極的に改善していこうという姿勢が見られないからです。
そして、その理由が先行する府県であまりうまくいっていないというものだとすると、これは残念を通り越して寂しい気持ちになります。他府県でうまくいっていないことを愛知でうまくやれば、さすが愛知県行政との評価になるのではないでしょうか。
そして、この鍵は公設民営だと私は思っています。愛知県には、この分野において日本屈指とも言える民間病院が存在し、この病院は県警との連携も十分に行われており、知事からの感謝状も受け取っている先です。ぜひともこうした先から知恵を借りてはいかがでしょうか。
愛知県が全国の先陣を切って公設民営でこの事業を軌道に乗せれば、壇上で申し上げた利点に加えて、諸外国対比で評価が低いというふうに言われている日本の法医学者の地位向上や、赤字経営が多いと言われている民間病院にとって新たな収益源となる可能性なども期待できるはずです。
実は、厚生労働省はこの公設民営の構想を内々知っており、前向きな姿勢を見せています。あとは愛知県が重い腰を上げるだけです。
ぜひとも県民のため、国民のため、当該モデル事業への取組を強く、強く要望します。
以上で終わります。
あいち民主の黒田太郎です。
私からは大きく四つの質問をさせていただきます。
まず初めに、不耕起V溝直播栽培による米作りについてです。
私たちが今、生活する上で直面している課題の一つに、物価高があります。この課題に対して、国も自治体も様々な対策を講じているわけですが、物価高の生活への影響を緩和するには、一、収入を増やすこと、そして、二、物価を下げることのいずれかないしは両方を行う必要があるわけですが、私は今回の質問の中で、後者の物価を下げることについて考えてみたいと思っています。
では、物価を下げるにはどうすればいいのでしょうか。これも単純に考えると二つの手段があり、一、供給量を増やすか、二、生産コストを下げるか、いずれかないし両方を行うと、物価は下がることになります。
そして、今、物価高で私たちの生活を圧迫しているその象徴的な品といえば、それは米ではないでしょうか。
そこで、私は、米の値段を下げるため、米の生産コストを下げることができないかを考えてみました。
このことを考える際に、大変印象的な記事がありましたので、御紹介させていただきます。
週刊ダイヤモンドの二〇二四年五月十一日号には、埼玉県にある農業法人のヤマザキライスでは、玄米一キロを生産するのにかかる費用が七十五円、全国平均の費用は二百四十六円と書かれていました。そして、この経費節減を実現した栽培方法が乾田直播であるとのことです。
この乾田直播については、週刊ダイヤモンドの二〇二五年四月五日号にも取り上げられており、そこには植物活性剤などを併用して乾田直播栽培を行うと、稲作には不向きとされていた北海道の畑作地帯でも米作りが可能になると書かれており、米耕作地拡大、つまり生産量増加の可能性についても触れられていました。
では、乾田直播による米作りとはどういうものか確認してみます。漢字がまさに乾いた田んぼに直接まくということからも分かるとおり、畑状態の田に種子をまき、苗が立ってきたところで水を入れるという稲の栽培方法です。
一般的な水稲栽培では、まず、苗代で苗を作り、田では固まった土を掘り起こして空気に触れさせる田起こしを行った上で、もう一度さらに細かく砕き、田に水を張り、土とかき混ぜ、土の表面を平らにする代かきを行います。
この比較からも分かるとおり、乾田直播では苗を作る必要がなく、代かきも不要であるため、作業の省力化やコスト削減が期待できることになります。
ここで改めて乾田直播の長所を整理してみます。
まずは省力化です。
苗を育てる育苗、代かき、育った苗を田に植える移植が不要となるため、農家は他の作物の栽培や経営活動に時間を割けるようになります。
次に、コスト削減です。
育苗にかかるコストがなくなるほか、初期段階で田に水を張らないため、水管理のコストや水資源使用のコストが抑えられます。また、水使用量の削減により環境負荷が軽減されると考えられるほか、水を張っていない状態ではメタンガスの発生が少ないと言われており、これらの点で環境に優しいと考えられます。
もちろん、どんな物事も長所だけというわけにはいかず、短所もあります。乾田直播の短所を整理してみます。
まず、収穫量の年次変動が大きいと言われています。
また、田に水を張らない期間が長い分、雑草が育ちやすく、雑草管理が難しいと言われています。
さらに、新たな機械設備が必要なため、初期投資が大きいとも言われています。
加えて、乾田直播に適した品種が限られているとも言われています。
全体として、これまでの水田稲作とは異なる稲作であるため、技術の習得に難しさがあると言われています。
こうした短所があったとしても、長所が大きいなら、短所を克服して長所を伸ばしていく政策を実施すべきであると私は考えます。
そして、愛知県農業総合試験場では、乾田直播栽培の一種である不耕起V溝直播栽培を開発し、普及を図っているとのことです。
そこでお伺いします。
一、不耕起V溝直播栽培とはどのような栽培技術で、一般的な移植栽培の米作りに比べ、どの程度の省力化、低コスト化につながるのかお聞かせください。
二、不耕起V溝直播栽培による米作りについて、愛知県の普及状況、課題及び今後の取組方針についてお聞かせください。
次に、第二十回アジア競技大会における総合格闘技について伺います。
総合格闘技が来年のアジア競技大会の競技種目に追加されたと発表されました。この質問では、アジア・アジアパラ競技大会がより充実したものとなり、県民の皆様の税金を使って開催してよかったと思っていただける大会となることを願い、幾つかの問題点を指摘させていただきます。
まず、世界的に総合格闘技の団体は幾つかあるわけですが、来年のアジア競技大会の競技種目に追加された総合格闘技の団体は、アジア総合格闘技協会、アジアン・ミクスド・マーシャル・アーツ・アソシエーション──以下AMMA──であり、競技はAMMAが実施する形式で行われるとのことです。
しかし、このAMMAは総合格闘技の世界では本流ではありません。本流はあくまでも世界百二十か国以上が加盟する国際総合格闘技連盟、インターナショナル・ミクスド・マーシャル・アーツ・フェデレーション──以下IMMAF──であり、そのアジア支部がAMMAFとなりますので、このAMMAFが実施する形式で行われるのであれば、アジア競技大会の盛り上がりも期待ができます。
なぜならば、IMMAF形式で行われる総合格闘技は、二〇三二年のオリンピック種目になる可能性があり、その傘下であるAMMAFの形式で競技が行われれば、観客動員もかなりの数が期待できるからです。
また、団体としての歴史にも大きな差があり、AMMAは二〇二二年に設立されたのに対し、IMMAFは二〇一二年の設立と、十年の差があります。そうだとすると、国際的な大会を運営する上で、知識や技術、コツなどの蓄積に大きな差があると推察されます。
さらに、実は、愛知・名古屋は、IMMAF系列のアマチュア総合格闘技において非常に重要な地域なのです。なぜならば、IMMAFが毎年行う世界選手権において、その日本代表監督を務めるのは、名古屋市出身で名古屋にて道場を運営する方であり、その道場には、世界選手権にて銀メダルを獲得した山口怜臣選手が所属しているのです。
愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会にて、こうした実力ある、しかも名古屋にゆかりのある監督や選手が関与、参加できれば、大会の盛り上がりに大きく寄与するのではないでしょうか。
この点、AMMAの傘下に一般社団法人ジャパンAMMA協会が設立され、本年六月十四日の報道用資料には、今後は、アジア競技大会でのメダル獲得に向け、総合格闘技を愛する国内選手に広く呼びかけ、最強の代表選手を選考できますよう準備を進めてまいりますとありましたので、個人的には一筋の光を見た気持ちになりました。
そこでお伺いします。
アジア競技大会における総合格闘技は、申し上げましたような課題を抱えていることから、県としてよりよい競技とすべく、何らかの対応をすべきと思いますが、県のお考えをお聞かせください。
次に、創業者を孤立させない取組について伺います。
昨年十月末にSTATION Aiが始動し、約八か月となります。この質問では、県民の皆様からお預かりした税金で造ったこの施設を日本一、世界一の施設にして、県民の皆様に恩返しをするために、大切であると思われる視点を提供させていただきます。
まず、プレ・ステーションAiも含め、これまでのSTATION Aiプロジェクトでの支援を通じ、どのような成果が生まれているかお伺いします。
そして、仮にプレ・ステーションAiの時代を通じて、数字の上では順調にスタートアップ支援が行われているように見えたとしても、この数字からは分からない問題が潜んでいます。それが創業者の燃え尽き症候群と言われる問題であり、私がこの質問で訴えたいことなのです。
それでは、まず具体例として、私の知人の状況を、知人了承の下、以下に整理してみます。
知人は新卒で製薬企業に入社。その後、留学を決意し、一年半で退職。英国で大学院修了後、外資系製薬企業の研究開発職に就き、帰国。その後、こうした経験を生かして起業することを決意。約一年半の準備期間を経て、主に承認後の薬の評価やエビデンス創出に焦点を当てた臨床研究支援の会社を起業した。
当然のことながら、起業には苦労があり、知人を含めた三人で事業を開始。資金節約のため、民家を借り、オフィス兼住居にした。起業当時、知人の業務内容は欧米では珍しくなかったが、日本ではほとんど知られておらず、会社規模も小さく実績もなかったため、理念や狙いは理解されても、業務依頼にはつながらない日々が続いた。
しかし、知人は努力を重ね、二十一年の間に、製薬企業に加え、大学や研究機関、行政機関から数多くの依頼を受け、国内外で実績を構築した。
また、働きながら国内外の大学院にて博士号や修士号を取得するメンバーを輩出し、国際的な人材の採用や海外企業との業務提携も実現した。大学との共同研究講座にも参画し、個人的にも、大学の兼任講師として研究や教育活動にも従事した。年商十億円の目標を除けば、それ以外は起業時の目標をほぼ達成した。 こうして見ると、この起業は、世間一般的に見れば成功したと言えよう。
しかしながら、身体に変調を来した。仕事をしながら息絶えてもよいという精神状態で、睡眠時間は一日平均三時間、会社で寝泊まりするということもしばしばといった働き方を続けたところ、原因不明の発熱に悩まされたほか、アトピー性皮膚炎の症状が全身に広がり、仕事が手につかない状態になった。精神的にも不安定となり、大口の出資者から社長を譲れという宣告があったことで、断腸の思いで社長を交代することになった。
自分の異変に気づいていたにもかかわらず、アクセル全開のまま立ち止まらずに放置し、結局は心身がむしばまれ、燃え尽きてしまった。このような自身の経験を生かし、現在ではスタートアップやベンチャーの創業者向けにカウンセリングやコーチングプログラムを開発し、提供したいと考えている。
以上が知人の具体例ですが、これが知人に限った話ではなく、スタートアップの世界においてよく見られる問題であることが最近分かってきたようです。
二〇二三年三月、イスラエルのコンサルティング企業、Y・ベンジャミン・ストラテジック・マーケティング社は、創業者が抱えるストレスとその影響についてまとめた報告書、スタートアップ・スナップショット第七版を発表しました。
この報告書の骨子は以下のとおりです。
四四%の創業者が強いストレスを感じ、三六%が燃え尽きの状態にある。
五四%の創業者が自社の未来に強い不安を感じている。
八一%の創業者が自身のストレスや不安についてあまり周囲に打ち明けられていない。
投資家に自分が抱えているストレスについて話すと回答した創業者は僅か一〇%。
カウンセリングやコーチングを受けている創業者は二割にすぎない。
そして、報告書のサマリーには、イノベーションの精神を持つ創業者たちだが、ストレスケアという点においては過去にとらわれていると書かれているとのことです。
米国では、スタートアップ企業の創業者のストレス対策を講じる動きが生まれているようです。例えば、投資家とスタートアップ創業者たちがメンタルヘルスケアの推進を宣誓するウェブページ、ファウンダー・メンタルヘルス・プリッジを公開したとのこと。このページには既に六百五十三名もの投資家や創業者が署名し、メンタルヘルスをビジネスの優先事項として取り組むことを表明しているようです。これは二〇二三年十一月現在です。
このように、華やかに見えるスタートアップの世界ですが、創業者の精神状況、特に燃え尽き症候群といった問題が着目され始めています。そして、燃え尽き症候群は創業者の抱える孤立感が大きな要因の一つと考えられます。
STATION Aiもこうした問題について配慮がなされれば、まさに日本一、世界一のスタートアップ支援拠点に進化していくのではないでしょうか。
そこでお伺いします。
創業者を孤立させないような取組として、STATION Aiではどのような支援を行い、成長支援につなげているのかお伺いします。
結びの質問は、死因究明拠点整備モデル事業についてです。
我が国は多死社会へ急速に移行しており、それは愛知県でも同じことです。
人口動態統計によりますと、愛知県内の二〇一四年の死亡者数は六万二千四百二十六人であり、これが二〇二四年の概算では八万二千六百九人と、この十年で二万人以上の増加があり、率にすると三二・三%も増えています。これが二〇四〇年には九万人を超えるとの予測もあるようです。
では、死亡者数が増えると、我々の社会にどのような影響が出てくるのでしょうか。これについては幾つもの影響がある中で、この質問では死因究明体制が追いついていかないのではないかという点に絞って考察してまいります。
それでは、死因を不明なままにしておくと、どのような問題が生じるのか、具体例を挙げて考えてみます。
例えば、独り暮らしの高齢者が自宅で死亡する、いわゆる孤独死の場合、遺体が数日後に発見されることがあり、その場合は検死──これは警察による検視と医師による死体検案の双方を含む──が困難で、死因が不詳とされたり、心不全などの曖昧な死因で済まされてしまうことがあります。
しかし、死因が熱中症と確定できれば、エアコン設置支援という政策につながり、栄養失調と確定できれば、見守り訪問強化という政策につながり、服薬中断と確定できれば、配食・服薬支援の導入といった政策につながるといったように、具体的な政策につながるはずなのです。
また、例えば、糖尿病による死亡に地域差があることが正確に把握できていれば、地域別にきめの細かい生活習慣の改善指導を行うことができ、どの地域にも同じ指導を行ったときと比べて、指導の効果がより高まると推測されます。
このようにして考えると、死因の見える化は政策の羅針盤であると言えるのではないでしょうか。死因が不明なまま遺体を火葬することは、地域の健康課題を知るためのデータが焼失することを意味します。
こうした意味で、死因究明体制の整備は、医療、福祉、公衆衛生の方向性を示す羅針盤を県政に設置するための投資であり、多死社会に対応するための基幹インフラ整備であると言えるのではないでしょうか。
では、死因は現状、どの程度正確に把握できているのでしょうか。
警察庁の死体取扱状況によれば、二〇二四年に愛知県警が取り扱った死体数は九千三百十九体、このうち解剖された数は四百五十四体、解剖率は四・九%と、全国平均九・八%に比べて低くなっています。
しかし、解剖以外にも遺体をCTでスキャンする死後CTという検証方法があり、これは約三千体行われています。この死後CTは死因究明における重要な情報源として活用されており、一定程度、死因の絞り込みや判定の精度向上に貢献していると考えられます。したがって、解剖と死後CTを加えた三千五百体は、かなり詳細な死因が把握できていることになります。
しかし、残りの約六千体の死体については、臨床医による検案などを基に死因が判断されており、これらが公衆衛生や予防医学の観点から十分な精度を持って死因特定がなされているとは限らないという課題も指摘されています。 また、昨年の死者数が八万二千六百九であり、そのうち、警察が取り扱った死体数が九千三百十九であるため、その差の約七万三千体については、事件性がなく、病院などで亡くなられたことによるものですが、臨床現場では医師の経験と判断に基づいた診断が行われており、制度としての検証体制が十分に整っているとは言い難く、老衰や心不全などの包括的な診断名で処理される例も少なくありません。その結果、公衆衛生上の課題や地域の疾病実態が統計上で捉えにくくなるという問題が指摘されています。
このように、警察が取り扱う遺体も、それ以外の遺体も、医療、福祉、公衆衛生の観点からの死因究明が十分にはなされていないという点については、愛知県に限った問題ではありません。
こうした実態を受けて、厚生労働省では、死因究明等の実施に係る体制の充実強化は喫緊の課題と認識し、死因究明等推進計画を二〇二一年六月一日に閣議決定、二〇二二年度から死因究明拠点整備モデル事業を実施しています。
この事業には、一、検案・解剖拠点モデル事業と、二、薬毒物検査拠点モデル事業の二つが含まれていますが、本質問では前述の流れを受けて、一について取り扱わせていただきます。
そして、検案・解剖拠点モデル事業とは、この募集要項の取組の具体イメージのところに、都道府県警察、法医学教室、地元医師会等の地域における死因究明に取り組む関係者と連携・協力の上、都道府県知事部局等に死因究明拠点を設置するとあります。
愛知県として、ぜひともこのモデル事業に手を挙げていただきたいというのが、私がこの質問において強く訴えたいことなのです。
死因の見える化は政策の羅針盤、死因究明体制の整備は多死社会に対応するための基幹インフラ構築と申しましたが、もう少し具体的に、県がこのモデル事業を進め、死因究明体制を整備したときの利点、欠点を整理してみます。
まず、利点です。
一、御遺族の心理的、法的負担が軽減されます。
死因が不明なままでは、なぜ亡くなったのかという最も根源的な疑問が残り、遺族にとっては深い心理的負担となります。また、相続や保険等の法的手続にも支障を来すことがあります。
二、社会的リスクの見逃しが軽減されます。
例えば、独り暮らしの高齢者の死亡原因が不詳とされれば、本当は熱中症や栄養失調、服薬中断などがあったとしても見逃されます。すると、県としてどこに何をどれだけ支援すべきかが分からず、見守り支援や配食サービスといった施策が的外れになり、結果として税金の浪費にもつながります。
三、地域課題、環境リスクへの対応を早めます。
ある地域で特定の病気による死亡が増えていたとしても、死因が不明なままではその傾向に気づくことができません。仮に環境汚染や新たな感染症が背景にあった場合でも、早期対策が打てず、後手対応になってしまうおそれがあります。
四、医療の質を向上させます。
医療機関での急死や手術中の死亡においても、解剖による検証がなければ、医療の質向上や医療事故の防止に資する情報還元がなされません。
五、虐待、ネグレクトの兆候見逃しを防ぎます。
家庭内での死亡や介護中の急変の中には、一見、自然死に見えても、実は虐待やネグレクトが隠れていることもあります。適切な死因究明が行われなければ、こうした見えにくい人権侵害が放置されてしまう危険があります。
六、警察の負担が軽減されます。
検査施設において、遺体搬送、検案及び遺体の引渡し等を集約して行うことで、現状、警察官が行っている搬送等の業務が不要となります。
七、災害時などの遺体渋滞が緩和されます。
遺体渋滞とは、大規模災害時に多数の死者が短期間に発生することで、遺体の収容、搬送、検視・検案、安置、引渡しに至る一連のプロセスが円滑に進まず、深刻な滞留状態が生じることを指し、昨年元日に発災した能登半島地震をはじめ、大規模災害時に発生する深刻な問題です。
では、県にとっての欠点は何でしょうか。それは、財政支出を伴うということかと思います。
しかし、県民の皆様からお預かりする税金を何に使うか考えるとき、単に支出を支出とだけ片道で捉えるのではなく、その支出によって県民の皆様にどのような便益がもたらされるのかを考えるべきで、そうした観点で見れば、上記七つの利点は財政支出に十分資する利点と言えるのではないでしょうか。
そこでお伺いします。
愛知県として、死因究明拠点整備モデル事業にどのように対応していくお考えか、お聞かせください。
以上で、私の壇上からの質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◯農業水産局長(松井直樹君)
不耕起V溝直播栽培についてのお尋ねのうち、初めに、不耕起V溝直播栽培がどのような栽培技術で、どの程度の省力化、低コスト化につながるのかについてお答えします。
不耕起V溝直播栽培は、米作りの省力化と経費の削減を目指して、県農業総合試験場が一九九四年に開発しました。現在、全国二十三の道府県で導入されている栽培技術となっております。
この技術の特徴は、春先に乾いた田を耕さず、専用の機械でV字型の溝を切り、その溝に種もみと肥料を同時に直接まくところにあります。また、種もみが成長し、田に水を入れた後は収穫まで水を抜かずに栽培することから、水管理の省力化と夏の高温対策に効果があります。
このように、不耕起V溝直播栽培は、一般的な米作りに比べ、育苗や田植の作業が不要となり、水管理の手間も省けることなどから、労働時間が約三割削減できます。また、育苗資材が不要となることなどから経費が約一割削減でき、省力化と低コスト化を兼ね備えております。
次に、不耕起V溝直播栽培について、愛知県内の普及状況、課題、今後の取組方針についてお答えします。
不耕起V溝直播栽培は、省力化や低コスト化、さらには栽培時期の分散などのメリットがあることから、大規模な経営体を中心に、二〇二四年は県内の作付面積の約一五%に当たる約三千八百ヘクタールで取り組まれております。
不耕起V溝直播栽培を実施する上での課題としましては、専用の機械導入のために初期投資が必要であることや、春先に田に水を張らない期間が長く、雑草が生えやすいといったことがあります。
こうしたことから、機械導入に際して国や県の補助事業により支援するとともに、現在、農業総合試験場と民間企業が協力して開発を進めている雑草対策技術の早期実用化を図るなど、農業者が取り組みやすい環境を整え、米作りの省力化、低コスト化につながる不耕起V溝直播栽培の導入拡大を今後とも推進してまいります。
◯アジア・アジアパラ競技大会推進局長(舛田崇君)
第二十回アジア競技大会における総合格闘技についてお答えいたします。
総合格闘技につきましては、昨年九月に開催されたアジア・オリンピック評議会(OCA)と組織委員会が準備の進捗状況等について協議、調整を行う調整委員会の第二回会議において、OCAから実施協議に追加するよう要請がありました。
これを受け、組織委員会理事会での報告を経て、本年五月開催の第三回OCA調整委員会において、コンバットスポーツの一種別として追加することが決定されたところでございます。
一方、総合格闘技には複数の競技団体があり、それぞれの団体が大会を主催し、競技運営等を行っています。
アジア競技大会においては、OCA憲章により、OCAが承認した機関が技術面の運営の責任を負うと規定されていることから、愛知・名古屋二〇二六大会では、OCAに承認されたアジア総合格闘技協会と組織委員会が責任を持って競技を実施するものと認識しております。
また、日本選手団の派遣につきましては、本年五月に設立された一般社団法人ジャパンAMMA協会により、選手の選考を行うことが公表されております。 総合格闘技がアジア競技大会の正式競技として実施されるのは、愛知・名古屋二〇二六大会が初めてとなります。
県といたしましても、日本代表選手が活躍し、競技が大いに盛り上がるよう、選手の派遣を行う日本オリンピック委員会に対し、選手強化やトップクラスの選手派遣について要請を行ってまいります。
さらに、この初開催の競技をより多くの方に会場で御覧いただけるよう、地域のイベントなどを通じて、県民の皆様への周知も図ってまいります。
大会の開催に向け、組織委員会や競技団体など関係者一体となり、総合格闘技のみならず、全ての競技がベストな状態で行われるよう、準備を進めてまいります。
◯経済産業局長(犬塚晴久君)
STATION Aiプロジェクトにおける成果についてお答えいたします。
県では、二〇一八年十月に策定したAichi─Startup戦略に沿って、ハード・ソフト両面で起業家の裾野の拡大から創業、その後の事業展開に至るそれぞれのステージにおける支援や、地域全体のスタートアップ・エコシステムの醸成に努めてまいりました。
二〇二〇年一月に開設したプレ・ステーションAiでは、創業期、事業化初期を中心とした支援を実施し、昨年十月にオープンしたSTATION Aiでは、海外展開や事業会社とのオープンイノベーションを含む事業拡大も含めたオールステージに支援対象を拡充し、引き続き、切れ目ない支援に取り組んでおります。 これまでのSTATION Aiプロジェクトにおける支援を通じて、百五十七件の起業、百四十五件の資金調達、五十六件の人材採用、七十三件の事業会社との事業連携に加え、スタートアップの出口戦略、いわゆるエグジットとして、二件のM&A、一件の株式公開といった事例も出てきております。
具体的には、AIを活用した越境ECプラットフォームを展開する株式会社サゾが今年五月に七億一千万円を資金調達し、現在、STATION Aiに本社を構え、事業展開を進めております。
また、eスポーツ大会支援ツールの開発・運営事業を手がけていた株式会社パピヨンが上場企業へ事業売却、いわゆるM&Aを実現したほか、小型ドローンの開発、画像データの解析サービスを展開する株式会社リバラウェアが東証グロース市場へ上場、株式公開いたしました。
今後とも、こうした取組を一層強化し、スタートアップの創出、育成、事業拡大をしっかりと支援してまいります。
次に、STATION Aiにおける創業者を孤立させない取組についてお答えいたします。
創業者が事業を立ち上げ、成長させていく過程では、資金調達、人材確保、知的財産保護、社内ガバナンスの確立といった様々な課題を乗り越えていく必要があり、そのためには創業者の孤立を防ぎ、精神的なフォローや仲間づくりを支援していくことが大変重要と認識しております。
このため、STATION Aiでは、コミュニティマネージャーを配置し、日常の相談対応のほか、毎月、創業者にマンツーマンで事業の進捗状況を聞き取るマンスリーアップデートの機会を捉え、ビジネス面の相談に加え、心身面の状態把握やフォローを行っております。
また、会員専用のコミュニティツールを活用し、会員同士の対話や交流イベントへの参加、個別相談への活用を促すなど、お互いの知識、経験を共有し、解決につなげていく環境づくりに努めております。
さらに、テーマを定めて十五人から二十人程度のより小規模で密に交流できるコミュニティーとして、ギルドと呼ぶ制度を運営しております。このギルドの中からは、自らの悩み、課題を創業者同士で共有し、先輩起業家の経験やアドバイスも聞きながら、課題を克服し、成長していくことを目指す活動も出てきております。
今後とも、創業者が創業者同士、専門家、先輩起業家と情報共有し、相談しやすい環境づくりに努め、より多くのスタートアップの成長支援に取り組んでまいります。
一点、訂正させていただきます。
先ほど、小型ドローンの開発、画像データの解析サービスを展開する株式会社の名前につきまして、私、リベラウェアと申し上げましたが、リバラウェアの間違いでございました。訂正させていただきます。失礼いたしました。
◯保健医療局長(長谷川勢子君)
死因究明拠点整備モデル事業への本県の対応についてお答えします。
死因究明は、災害、事故、犯罪等における被害の拡大や再発防止に寄与するとともに、疾病予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上に資する情報として活用されるなど、公益性の高い取組であると認識しております。
国が実施する死因究明拠点整備モデル事業は、公衆衛生の観点から解剖や検査等が適切に実施される体制の構築を目指す取組で、二〇二二年度の事業開始から毎年度、二、三か所の自治体、大学で、検案及び解剖のモデル事業が実施されております。
しかしながら、モデル事業の実施結果を見ますと、解剖や検査の件数は年間で数件程度にとどまっており、その要因として、画像診断医や解剖医の不足、協力検案医の確保、警察との連携等挙げられております。
さらに、こうした要因以外にも、遺体の搬送体制の整備や、遺族の理解と同意など、整理すべき課題は少なくありません。
このように、モデル事業の実施については、県警察、大学の法医学教室、県医師会などとの連携、協力が不可欠となりますので、関係機関の意見を伺いながら、しっかり研究してまいりたいと考えております。
◯経済産業局長(犬塚晴久君)
失礼いたしました。先ほど企業名の訂正をさせていただきましたけれども、正しくは小型ドローンの開発、画像データの解析サービスを展開する株式会社リベラウェア、リベラウェアが正しい名前でございました。失礼いたしました。
◯三十七番(黒田太郎君)
それぞれに御答弁ありがとうございました。
それでは、一点、要望させていただきます。
死因究明拠点整備モデル事業についてでございます。
答弁を聞き、残念な気持ちになりました。死因という今後の政策立案にとって極めて重要な情報が十分に把握されていないにもかかわらず、この状況を積極的に改善していこうという姿勢が見られないからです。
そして、その理由が先行する府県であまりうまくいっていないというものだとすると、これは残念を通り越して寂しい気持ちになります。他府県でうまくいっていないことを愛知でうまくやれば、さすが愛知県行政との評価になるのではないでしょうか。
そして、この鍵は公設民営だと私は思っています。愛知県には、この分野において日本屈指とも言える民間病院が存在し、この病院は県警との連携も十分に行われており、知事からの感謝状も受け取っている先です。ぜひともこうした先から知恵を借りてはいかがでしょうか。
愛知県が全国の先陣を切って公設民営でこの事業を軌道に乗せれば、壇上で申し上げた利点に加えて、諸外国対比で評価が低いというふうに言われている日本の法医学者の地位向上や、赤字経営が多いと言われている民間病院にとって新たな収益源となる可能性なども期待できるはずです。
実は、厚生労働省はこの公設民営の構想を内々知っており、前向きな姿勢を見せています。あとは愛知県が重い腰を上げるだけです。
ぜひとも県民のため、国民のため、当該モデル事業への取組を強く、強く要望します。
以上で終わります。